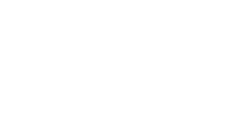ラクロス部の中で一番”入部回数”が多い男、けんごから回ってきました。
4年#77 DFの久枝海人です。
まず初めに、平素より上智大学男子ラクロス部をご支援いただいている保護者の方々、コーチの皆様、またOBOGの方々をはじめとした全ての関係者の方々に心より感謝申し上げます。今後も変わらぬご支援、ご声援のほどよろしくお願い申し上げます。
〜目次〜
1.振り返り
2.ラクロスを通して学んだ2つのこと
3.感謝パート
4.激励パート
1. 振り返り
ラクロス部に入部したきっかけは、自身の高校時代にあります。
当時はテニスに没頭しており、地元のテニスコートにある壁で壁打ちをするのが日課でした。
自分が壁打ちをしている隣に、ほぼ毎日同じ時間帯に1人のラクロッサー(確か青◯学院大学の方?)が来ていました。
「ここはテニス用の壁やぞ!!」と、若干の不満を募らせながらも、虫取り網みたいな不思議な棒でボールをバンバン打ち付けている姿を見て、「なんか面白そうなスポーツだな」と、気づけば興味を持っていました。
(今の自分ならその人の気持ちが分かります。近所に全く壁がないので。)
入部後は、毎朝4時半起きの生活。
想像していた大学生らしい自由でフレキシブルな大学生活とは180度違うものでした。
学業面では「1,2年のイスパの授業を落としたら詰み」であることを重々承知していたので、グラウンドに向かう電車の中やアルバイトの休憩時間で猛勉強しながら、部活と学業、そしてアルバイトの全てに全力で勤しんでいました。
サマー、ウィンター、あすなろ…。
大学生活の折り返し地点までは本当にあっという間でした。
そして迎えた、1年間のメキシコ留学。
部活動人生で一番濃い時間をみんなと一緒に過ごせなかったのは、正直とても悔しかった。
それでも、入学当初から「絶対にスペイン語を話せるようになる」と心に決めていたので、留学という選択をしたことに今でも後悔はありません。
そして、そんな自分を快く送り出してくれたみんなには、感謝してもしきれません。
Gracias a sus cooperaciones y apoyos, ya hablo español como mi segunda lengua materna.
現地では朝の2、3時に試合のライブ配信を見ながら、「みんなめっちゃ上手くなってるな〜」なんて、偉そうに観戦していたのを覚えています。
そして帰国後。
復帰早々に左足を怪我してしまい、幸先のいいスタートとは言えなかったものの、完全に抜け落ちてしまったラクロスの感覚を取り戻そうと、少しずつ感覚を探る毎日でした。
復帰のタイミングでは部内メンバーの半分以上が初対面という状況。
正直、不安でいっぱいでした。
その不安とは裏腹に、みんなが温かく迎えてくれたことが本当に嬉しかった。
心から「戻ってきて良かった」と、今この文章を書きながら思っています。
2. ラクロスを通して学んだ2つのこと
ラクロス部での活動を通して、大きく2つのことを学びました。
1つ目が、「あらゆる面で自責思考を持つ大切さ」です。
個人スポーツでは、ミスも敗北もすべて自分1人の責任です。結果は自分の行動の積み重ねなので、当然のことですよね。
でも、チームスポーツではそうはいきません。
みんながそれぞれの考えを持って動くからこそ、ときに意図がズレたり、思いが食い違ったりする。
さまざまな要因が複雑に絡み合い、「どこで、誰が、何を間違えたのか」が見えにくくなる。
当初の私は、どこかで他責思考をしていた部分がありました。
ディフェンス全体で起きたミスを、無意識のうちに「自分のミス」と「他人のミス」に分けて考えていました。
そして前者だけを反省し、後者については「自分は悪くない」「仕方ない」などと受け流していたのです。
しかし、振り返りを重ねる中で、チームスポーツでは一つのミスも個人の失敗に還元できるものではなく、チーム全体の動きの中で生じるものだという気づきを得ました。
そして、その結果に向き合う責任もまた、全員で共有すべきものだと考えるようになりました。
「自分はどういう声かけが足りなかったのか?」
「自分のアクションのどこが悪かったのか?」
すべてのミスに自分が関与していると考えると、チーム全体で同じ失敗を繰り返さないための糸口が見えてくる。
未来を変えられる可能性が自分の中にあると気づけたことが、大きな学びとなりました。
2つ目は、自分にとって「最初が9割」だということです。
「終わりよければ全てよし」という言葉が有名ですが、もちろんそれも正しいと思います。
しかし、自分にとっては、「最初こそが何よりも大切だ」と今は思っています。
これまでのスポーツ経験を振り返ると、水泳は幼稚園の年中から8年間、テニスは小学校6年生から7年間続けていたため、「新しいスポーツをゼロから始める」という経験は長い間していませんでした。
水泳では授業で無条件に最上級クラスに入れられ、テニスでは入学したての1年生ながら上級生の試合に出させてもらうなど、他の人よりも早くスタートラインに立てていたことで、多くの場面で優遇されていたと思います。
その環境に慣れていた私は、ラクロスを始めたときも心のどこかで「どうせできるだろう」と慢心していました。
しかし、現実はまったく逆でした。
技術も戦術理解も仲間のスピードに追いつかず、差は広がる一方。
1年生の時の練習試合では、戦術理解の甘さから同期に多大な迷惑をかけてしまいました。
そこからは何度も動画を見返してメモを書き殴ったり、夜9時からコーチにマンツーマンで44や66のシステムを教わったり。
自分が初期段階で苦戦している間に、仲間たちはさらに新しいことを吸収していく――。
そのとき、今まで気づかなかった自分の弱点を、真正面から突きつけられました。
「最初に死に物狂いで取り組まなければ、他の人よりも圧倒的に成長が遅れてしまう」
この挫折をきっかけに、自分の中で「最初」への向き合い方が大きく変わりました。
先輩からグラボのアドバイスをもらった日。
新しい練習メニューが導入された日。
塾のアルバイトで新しい生徒を担当した日。
メキシコに降り立った日。
日常の中で何か新しいことに取り組む際に、他の人と同様に、それ以上に良い結果を出せるように。
「新しいことを始めたその瞬間に、どれだけ死ぬ気になれるか。」
この学びは、これからの人生でも大切にしていきたい、自分の中の確かな信念になりました。
3.感謝パート
両親へ
ラクロス用品や部費、合宿費などの金銭面でも、早朝に起きなければならない時間面でも負担の大きいこのラクロスという競技を、続けさせてくれてありがとうございました。朝4時半に朝ごはんを用意しておいてくれたり、運動着や防具全てを洗ってくれたり。日々の支えの一つひとつが、本当に大きな力になっていました。これまでのサポートに心から感謝しています。これからもどうぞよろしくお願いします。
コーチの皆様へ
ラクロスの技術、そしてスポーツマンとしての姿勢までご指導いただき、本当にありがとうございました。日々の練習の中で教えていただいたことは、これからの人生でも大切にしていきたいと思います。今後も部員の技術や戦術理解の向上、そして1部昇格という目標の実現に向けて、上智大学男子ラクロス部を見守っていただけると嬉しいです。これまでのご指導と温かいサポートに、心より感謝申し上げます。
MG, TRのみんなへ
みんなからの多くのサポートに心から感謝しています。個人ではテーピングやケガの処置、チーム全体ではグラメや練習運営、ビデオアップなど、どれも欠かせないサポートばかりで、みんなの支えがなければ自分たちプレイヤーは今のように集中して練習に臨むことはできなかったと断言できます。
それぞれの役割で大変なことが多いと思いますが、これからもプレイヤーを支えていただけたら本当に嬉しいです。
晴れの日も雨の日も、暑い日も寒い日も、最高の練習環境を本当にありがとうございました。
同期へ
1人ひとりが強烈な個性を持っていて、毎日一緒にいても全く飽きることのない最高の同期でした。練習の中でお互いに高め合い、時にはぶつかり合いながらも勝利の喜びを分かち合えたことは、自分にとってかけがえのない財産です。
東京ドームの超高いBBQや、四谷のエアビ飲みなど、練習以外でも本当にたくさんの思い出ができました。
これからはそれぞれ別の道を歩むことになりますが、またどこかで集まって語り合える日を楽しみにしてます。
本当にありがとう。
4. 激励パート
まずは、たくみ。
3年生ながらディフェンスリーダーとして組織をまとめ上げるお前の姿に、脈々と受け継がれた「鞍掛イズム」を感じていた。
お前の持っているリーダーシップとガッツは、お前自身のプレーの向上にも、ディフェンス全体を引っ張るうえでも確実に活きていると思う。
来年はついに最高学年。今年得た多くの学び、そして感じた悔しさを存分に活かして、仲間達と共に、上智ディフェンスの黄金時代を築いてくれ。
そして、SSこと齊藤渉太。
留学から帰ってきて、一番変わったと感じたのは間違いなくお前だった。
かつては遅刻の常習犯で、どちらかといえば静かな印象だったのに、復帰した日の練習で見たお前はまるで別人だった。
正確なパス、66でディフェンス全体に指示を出す姿、筋トレに本気で取り組む姿、そしてタメで超フランクに話しかけてくれるところ。その全部が本当に衝撃で、圧倒的に成長したお前の姿を見られて心の底から嬉しかった。
来年はお前が文字通りチームの「守護神」になる番だ。
自信持って、胸張って、頑張れ。
----
さて!次は同期で唯一の浪人経験者、ざわです。
どれだけ走っても疲れを見せない、ターミネーターを思わせる「無尽蔵の体力」でオフェンスを支える彼。
脳震盪による長期の離脱を経験し、地道なリハビリの末に復活を果たした彼の思いとは――。
明日もお楽しみに!